
今回「日本語教師プロファイル」でお話を伺ったのは、名古屋のセントラルジャパン日本語学校主任教員である柏谷涼介さんです。「自分なんて思いつきで日本語教師になったので、キラキラしたところは何もないです」とおっしゃりながら、大変ユニークで興味深い教育実践をなさっている方です。豊富なアイデアが生まれる秘密はどこにあるのか。是非、お読みください。
行き当たりばったりで日本語教師養成講座に
――日本語教師になったきっかけを教えていただけますでしょうか。
外国語に興味があったとか、外国の生活や異文化に興味があったという方は多いと思うんですけれども、私の場合はそういうのが一切なくて。一言で言うと思いつきです。大学4年生の時、それなりに就職活動はしていたんですが、一番大きかったのが 働きたくない という現実逃避で。それで本屋に行ったら いろんな講座のパンフレットが置いてあって、そこに日本語教師養成講座があったんですね。これは日本人だからできるんじゃないかと。よくある誤解ですよね。それで、いつのまにか申し込んでたみたいな。大学は商学部だったんですが、全然勉強していなくてギリギリ卒業できたという感じです。だから、今、留学生で、将来どういう分野に進みたいか聞いても分からない学生が多いのですが、その気持ちは良くわかります。
――語学が好きというのもなかったのでしょうか。
うーん、洋楽が好きだったのと、子どもの頃から本を読むのは好きでした。それと自分の性格的に興味がないものを売ったりすることは多分できないと思っていたので、会社ではないところで働く方がいいんじゃないかなと思っていました。ただ自分で決断して行ったわりにはですね 、やっぱり養成講座もそんなに真剣に受けたっていう感じはなかったんですね。フラフラしていた。修了はして、日本語教育能力検定試験も受けたんですが、多分 マークシートのラッキーで、1回で合格できたので、一つ目の日本語学校に入ったって感じですかね 。
日本語学校で教え始めるも......
――日本語を教え始めていかがでしたか。
真剣に勉強してなかったせいもあると思うんですけれども、最初授業をどうやったらいいかわからなくて、でも何とかしなきゃいけないので、起きている間ずっとどうしたらいいのか考えていました。非常勤で右も左も分からない時に、初めから週4とか週5授業を持ったので、大変でした。20年以上前のことですが、学生はほぼ中国の学生でした。2年ぐらい後、学生数が減って、授業数が減るという話になったんですね 。それだったらやめようと思って、1年ぐらいやめていた時期があります。
――その時は何をなさっていたんですか?
今でいう派遣ですけど、日雇い労働でどこかの工事現場に連れて行かれて工事の手伝いしたりとか、ビルを解体したりとか、中部国際空港の仕事もしました。その頃、本当に何かになりたいという希望がなくて、日雇い労働で稼いだお金で全部お酒を飲んじゃうとか、お金がなくなったらまた働くみたいな生活を1年ぐらいしていました。夜の公園で一人で酎ハイ飲んで、「何やってるんだろう」と思ったり。26歳ぐらいの時です。
ある先生との出会いから
――その後、また日本語教師に復帰されるわけですね。影響を受けた方がいると伺いましたが。
男性の先生を希望しているという学校があったので教え始めました。そこで一緒に担当することになった先生がいるんですけど、その人の言っていることや、やっている授業にすごくショックを受けました。今までの自分は何をしていたんだろうと。勝手な敗北感みたいなのを感じました。別に厳しく言われたわけではないんですが、ただ私がその先生のことを見て、全然違う次元にいる人がいるんだと思い、そこから勉強をするようになりました。その人との出会いがなければ今の自分はないと思っています。
それから論文や書籍を多分2000ぐらいは読みました。初めは読んでも何が書いてあるのか一切分からなかったのですが、読んでいくとだんだん分かるようになり、いろんな知識がついて、それをじゃあ実践でどうしたらできるかをすごく考えるようになりました。
私が好きなのは第二言語習得で、今では大学の第二言語習得の科目も持って教えています。他にはCLILが好きです。例えば地雷について学んで、その中で 日本語をもちろん勉強するんですけど、最後に地雷反対の詩の朗読ムービーを作ったり、日本の震災について学んで「花は咲く」のミュージックビデオを作ったりとか。公共広告のCMを作ったりとか、そういう授業がすごく好きで、10年ぐらい前からずっとやってますね。
ユニークなカリキュラム
――現在のセントラルジャパン日本語学校でのお仕事について教えてください。
現在は主にカリキュラム作りと養成講座を担当しています。大学でも授業を持っていますし、大学生の教育実習も受け入れています。それから地域日本語教育アドバイザーをしています。あと最近だと、文科省の委託事業の「日本語教育の参照枠」を活用した教育モデル開発・普及事業にも携わっています。
外部との関りのある仕事が多いですね。
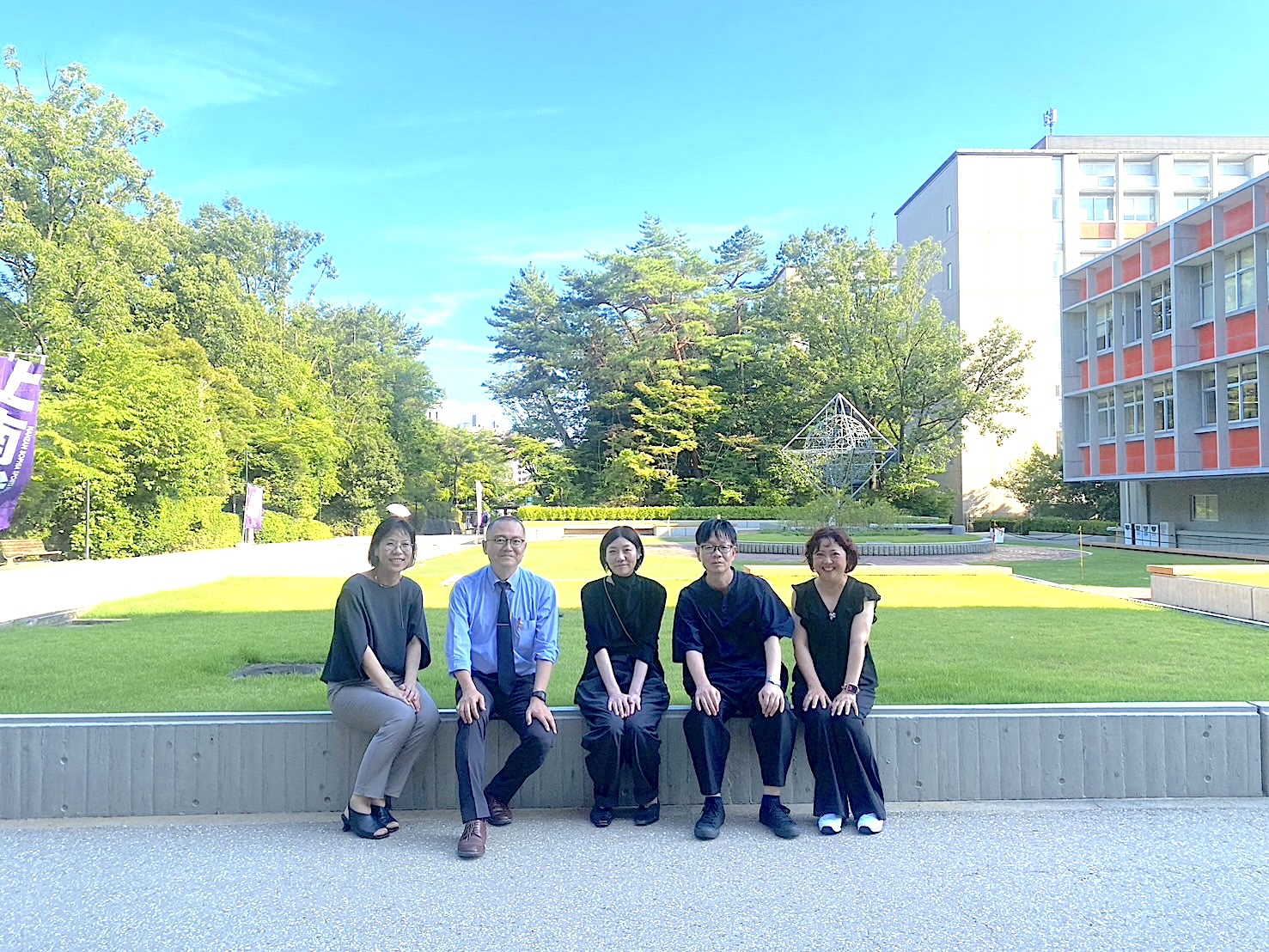 「日本語教育の参照枠」を活用した教育モデル開発・普及事業のチーム。通称〔wakame5〕
「日本語教育の参照枠」を活用した教育モデル開発・普及事業のチーム。通称〔wakame5〕
――御校のカリキュラムは他の日本語学校とは違ってかなりユニークだと思うのですが。
そうですね。初級は教材として『いろどり 生活の日本語』(国際交流基金)を使っているのですが、その後は1日4コマを前半2コマ、後半2コマの二つに分けて「対話」「自律」「日本の人と社会」「ノートテイキング」などの科目があります。「対話」という科目では「愛とは何か」「普通とは」「結婚すべき?」などをみんなで対話します。テキストは、初めは『「読む」からはじめる日本語会話ワークブック』(アルク)を使っていて、上のクラスは日本の中学生が使う哲学の本を使っていますね。哲学的な対話をすると、学生の力が必ずしも日本語能力と比例しているわけでもないんです。教室の中でいろいろな能力を持った人がいろんな時に活躍できるといいなと思います。
「日本の人と社会」という科目では 『The Great Japanese 30の物語 中上級 人物で学ぶ日本語』(くろしお出版)という教科書を使っています。これは本田宗一郎等日本の著名人のストーリーを通して学ぶものです。
他に「自律」という科目もあります。これは自律的に学習していける学習者を育てるという科目ですが、その中で参照枠やCEFRの理解もやります。それで学生も参照枠のことを知っているんです。実はこんなエピソードがありました。ある進学説明会で学生が大学の先生にN2を求められたそうです。でもその学生はN2に合格してないんですね。ちょっとしょんぼりしてたら、別の学生が「CEFRのことを思い出せよ。JLPTが全てじゃないんだよ。あれで全部測れるわけじゃないんだよ」そういうことを言って励ましていたそうです。学生の方が参照枠を正しく捉えているんです。
一人一台のノートパソコン、AIも活用
――ICTにも力を入れているそうですが。
学生には一人一台ずつノートパソコンを配布しています。最初はタイピングから初めて、スライドを作る授業もあります。去年からはAIも授業に取り入れ、自分の日本語をチェックしてもらうことも授業の中でやっています。
学校って全部のリソースをはく奪された裸の姿で勝負させられるじゃないですか。テストにしても何しても、 辞書を使っちゃいけないとか友達に聞いちゃいけないとかっていうことをしているのって学校だけだと思うんです。一方、何を使ってもいいから、いい結果を出すっていうのが実際の社会ですよね。学校だけそういうことをしていると現実の世界とだいぶ離れてしまう。使えるものは何でも使って、それも含めてその人の能力だと考えています。丸裸の状態じゃなくて、辞書を使える、電卓を使える、 AI を使える、なんか日本語が上手な友達がいる、とかですね。その関係性の中にその人の能力があると考えるようにしています。
――それが授業設計の中に落とし込まれているんですね。
カッコよくいうとそうですかね。テストもスマホとかパソコンを使ってもいいテストがあったりするんですよ。 もちろん 何も使わないテストもあるんですけど、 例えば書くテストとかはスマホとか使っていい、在留カードも見ていい、としています。
――JLPTやEJUなどの試験対策についてはいかがですか。
試験対策を全然やっていないわけではありません。1週間に2コマはその時間を取っています。ただ、ほとんど自習みたいな感じですね。インターネット上に試験対策問題が何百問も作ってあって、それを自分でやる、分からない時は先生に聞くという形です。スマホでもパソコンでもできます。開校する時に先にそれらの問題を作っておいたんです。試験対策というのはどうしても学校でやらなきゃいけないわけではなくて教室外でもできるものなので、自分のペースでやってほしい。それで学校では先生やクラスメイトがいる時じゃないとできないことをしてほしいと思っています。
ポジティブな振り返りをするために
 養成講座で、音楽制作ソフトを使った聴解教材の作成方法を説明しているところ
養成講座で、音楽制作ソフトを使った聴解教材の作成方法を説明しているところ
――とても興味深いカリキュラムですが、先生方の中には戸惑いの声はありませんでしたか。
そうですね。そんな声もあったかもしれません。ただ、このカリキュラムはこういう目標ですよとか、参照枠の言語活動や言語能力や方略等を表にして、ここがこの科目と関係が強いものですよと伝えるようにしています。迷った時には、今やっていることがこの表とあっているかを考える。原理原則に立ち返る、そこを見てもらって判断してもらいます。講師研修には力を入れているつもりなので、先生方の参照枠の理解は進んでいると思います。AIの使い方の研修も行っています。
よく学期の振り返りを講師会でやりますよね。でも学生のできないところとか、こういうところがうまくいかなかったとかそういう振り返りになることが多いと思うんです。もう少しポジティブな振り返りができないかと考えて。参照枠って学習者のできることを見るじゃないですか。だから学習者のできることを見つけてポジティブな振り返りをするために、クラスのテーマソングを作ろうというのをやったんです。変わったこと、できるようになったことを箇条書きで挙げていって、それを歌詞っぽい表現に変えてAIに曲をつけてもらった。それを使ってクラス担当の先生が歌詞を説明しながらクラスのことを伝えました。学校全体がポジティブな雰囲気になって、とてもよかったと思います。
言語教育者としてやっていきたいこと
――地域日本語教育ではどんなことをなさっていますか。
日本語の教え方というよりは、どうやったら外国語を勉強する人の気持ちになれるかについてお話しています。主に地域のボランティアの方対象ですが、やはり自分が受けてきた英語教育のイメージが強いと思うので、文法ばっかりにならないように、人間が言語を覚える仕組みを分かりやすく伝えたり、相手に伝わる言葉を使ってお互いのことを知る時間を持つのが大事なことですよとお話します。そうすること自体が日本語の練習になっているので、そんな関わり方をするといいんじゃないですかね、とか。ある地域でそういうお話をしたら、うちでもやってほしいと言われて、大体東海地方が多いですが、愛媛や高知や冨山などにも出向きました。
――これからのことで考えていることは何かありますか。
私は学校のカリキュラムを考える立場ですが、今やっているいろいろな授業活動を、日本語学校が終わった後に、ちょっと思い出してもらえるといいなと。人生っていろいろ浮き沈みがあって辛くなる時もあると思うんです。そんな時、あの時作った歌聞いてみようかなとか、あの時ベトナムのクラスメイトとふざけたムービー作ったよなとか、日本語学校にいる時間が、後でちょっと思い出してくすっとなって、また次の日に人生をつないでいけるような時間にできるといいなと思っています。日本語を身に付けることももちろん重要なんですけど、そういう2年間とか1年半になることの方がもっと大事なんじゃないかなと思いますね。
もう一つ最近考えているのは、「日本人ファースト」って言葉が出ていましたよね。あれがすごく引っかかっていて。外国人が優遇されているっていうデマが流れています。なので、それに対してきちんとしたデータを出して、「こういうデータがあります。だからこれはデマですよ」という話をしていきたいです。養成講座でもやりましたし、大学や地域のセミナーでも話しました。そこの部分で自分が大きいことができるとは思わないんですけれども、事実ではないことを誤解している人が多いと思うので、その誤解を解くことはしたい。そんな高尚な目標があるわけじゃないですけど言語教師、言語教育者としてやっていく必要があると思います。
日本語学校の場合、学校や教室という装置の中で、教師であることや母語話者であることというのは、やっぱり権威性を帯びやすいことであると思うんですよね。そのことに自覚的になることがすごく大事なことじゃないかなと思っています。
天才じゃなければ体力を
――これから日本語教師になりたい方にどんなことを伝えたいですか。
あまり一般的なアドバイスじゃないかもしれませんが、まず大切なのは「体力」です。体力があれば永遠に考えられますから。天才なら別ですけどね。天才じゃない限り「体力」だと。私は特別、才能や能力があったと自分で思いませんが、体力はあったんです。だから永遠に考えられた。そうするとアイデアが出てくるんです。そして体力があればチャンスも活かせますよね。例えば新しい仕事を頼まれた時、忙しくても体力があれば、その仕事を受けて自分の成長につなげることができるんです。 頭を使うのも頭だけじゃないので体力があることは有利だと思いますね。
――なるほど。御校にはどういう人に教師としてきてほしいですか。
柔軟な人ですね。経験がある方だといい面もありますが、過去の成功体験、過去の常識を捨てられないという人も中にはいるので……。「対話」だとか「自律」だとかの授業だと、今まで経験してきたことと全く違うと思うので、それを面白いと思って一緒にやってくれる人が有難いです。
セントラルジャパン日本語学校:https://cj-manabi.nagoya/
取材を終えて
お話を伺って、日本語学校といっても、いろいろな学校があるなあと思いました。そして何より楽しそうです。柏谷先生は自分が自由にやれるポジションにいるのもすべて運と縁のおかげですともおっしゃっていました。
取材・執筆:仲山淳子
流通業界で働いた後、日本語教師となって約30年。8年前よりフリーランス教師として活動。



